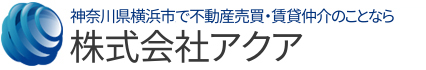家族や親戚が亡くなり財産を相続する場合、「相続税」が発生する可能性があります。高額になることも多い相続税が、相続した方の金額的負担になることも少なくありません。
そのような負担を少しでも軽減するため、相続税にはさまざまな特例や控除制度が設けられています。主なものをご紹介します。

■基礎控除
基礎控除は、相続税を算出する際に遺産の総額から一定の金額を差し引くものであり、すべての相続人に適用されます。
控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められます。例えば、遺産総額5,000万円で法定相続人が2人の場合、基礎控除額は3,000万+600万×2人=4,200万円となり、5,000万円から4,200万円を引いた残りの800万円が相続税の課税対象となります。
■小規模宅地等の特例
土地を相続した際は、小規模宅地等の特例が利用できることがあります。被相続人(亡くなった方)が住んでいた宅地や事業のために使っていた宅地、貸していた宅地などが対象で、減額率は最大で80%になります。
土地は高額なことが多いので、減額によってかなりの負担軽減に繋がるでしょう。利用条件や面積の上限など宅地の種類によっても異なるため、しっかりと確認しましょう。
■配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者には、税額軽減(配偶者控除)の制度が設けられています。控除額の上限は、「1億6,000万円」もしくは「法定相続分相当額」のどちらか大きいほうが適用されます。
仮に遺産総額が4億円で配偶者の相続分が1億8,000万円だった場合、「1億6,000万円」は超えますが、「法定相続分相当額」が遺産総額の1/2で2億円となるため、1億8,000万円の相続分には相続税はかからないということになります。
■未成年者控除
相続人が未成年者の場合に適用となる控除制度もあります。控除額は「10万円×(18歳-相続時の年齢)」で算出されます。
相続時15歳だった場合は、10万円×(18歳-15歳)=30万円となり、相続税から控除されます。
■障害者控除
85歳未満の障害者を対象とした控除制度もあり、控除額の計算方法は「10万円×(85歳-相続時の年齢)」です。
特別障害者の場合は「20万円×(85歳-相続時の年齢)」で、相続税から控除される額が決まります。
相続税の特例や控除は、相続する方の負担を減らし今後の生活を守るためと考えられます。
利用するには、適用となるさまざまな条件があります。いざというときに最適な方法が選択できるよう、知識を深めておきましょう。
株式会社アクアでは税理士業務の相談には応じられませんが、成年後見や相続、任意売却などに対応しております。
【任意売却や空き家対策】などの無料相談も行ってますのでお気軽にご相談ください。