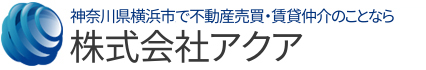家族が亡くなったあと、不動産を相続したものの、住む予定もなくそのまま放置している——そんな空家問題は全国的な課題です。
特に都市部から離れた住宅や築年数の古い戸建ては使い道が見つからず、管理されないままになることも多くあります。
しかし、相続した空家を放置することは、不動産相続のトラブルの引き金になりかねません。ここでは、空家処分、空家売却、インスペクション、相続登記の観点から、空家の正しい取り扱いと手続きのポイントを解説します。

空家を放置するリスクとは?
空家を放置すると、以下のような問題が発生します。
- 雨漏りや老朽化による倒壊リスク
- 雑草や害虫による近隣トラブル
- 不審者の侵入や放火など治安の悪化
- 固定資産税や火災保険料など維持費の負担
さらに、状態が悪化すると「特定空家」に指定されることがあり、固定資産税の軽減が外れたり、行政から修繕命令・過料が科されることもあります。
相続したらまず「相続登記」を済ませる
空家を活用・売却するには、まず不動産の所有権を自分名義にする相続登記が必要です。2024年4月からはこの手続きが義務化され、登記を怠ると最大10万円の過料が科される可能性があります。
名義が変更されていない状態では、売却や解体などの手続きが進められません。
戸籍謄本や遺産分割協議書が必要ですが、不安があれば司法書士への依頼が安心です。
空家の現状を把握する「インスペクション」の活用
登記完了後は、空家の物理的な状態を確認しましょう。古い建物では見た目がしっかりしていても、内部に劣化があるケースも珍しくありません。
そうした不具合を把握するのに有効なのが、インスペクション(建物状況調査)です。
建築士など専門家が行う調査では以下を確認します。
- 基礎や屋根の劣化
- 水回りや電気設備の不具合
- 雨漏りやシロアリ被害
- 建物の傾きやひび割れ
調査結果は、方針決定や買主への説明資料としても役立ちます。
売却か解体か?方針は柔軟に決める
調査結果や立地、築年数をふまえ、以下の選択肢を検討します。
- そのまま維持・管理して賃貸などに活用
- 老朽化が進んでいれば解体・更地にする
- 建物付きの状態で売却を目指す
近年はリフォーム前提で購入を希望する買主も多く、「古いから売れない」とは限りません。物件の特徴に応じた売却戦略が重要です。
空家売却の準備と手続きの流れ
空家を売却する基本的な流れは次のとおりです。
- 不動産会社に査定を依頼し価格を把握
- 必要に応じて軽微な補修や整地を検討
- インスペクションや登記情報を整理
- 買主決定後、売買契約と引き渡し
相続直後は関係者の意見が分かれることもあるため、手続きを段階的に進めることが成功のポイントです。
まとめ:空家は「放置せず、整えて動く」が鉄則
相続した空家を放置すると、資産どころか負担に変わる可能性があります。
相続登記を早めに済ませ、インスペクションで現状を確認し、適切な処分・売却を計画的に進めることが大切です。
「空家をどうすべきかわからない」という方は、まずは専門の不動産会社にご相談ください。状況に応じた解決策をご提案いたします。