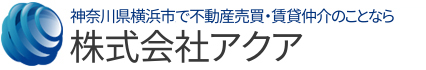親や親族の他界によって、突然不動産を相続することになる方も多いでしょう。中でも、誰も住んでいない「空家」を引き継いだ場合、そのままにしておくのは避けたいところです。
放置された空家は、老朽化による危険だけでなく、防犯・衛生面でも近隣に悪影響を与える可能性があります。
この記事では、相続後にすべき対応や選択肢、注意点を分かりやすく解説します。

まず最初に行うべきは「相続登記」
不動産を相続した際、最初に必要となるのが相続登記(名義変更)です。2024年4月からは相続登記が義務化されており、相続人は取得を知ってから3年以内に登記を完了しなければなりません。怠ると、最大10万円の過料が科される可能性もあります。
登記手続きでは、戸籍謄本や遺産分割協議書などの準備が必要です。専門的な書類が多く戸惑うこともありますが、司法書士へ依頼すればスムーズに進めることができます。
空家の状態確認は「専門的な診断」が鍵
相続した空家の取り扱いを考えるうえで、まず押さえておきたいのが「建物の状態」です。ここで活用されるのが、建物状況調査(インスペクション)という専門的な診断サービスです。
この調査では、建物の構造や設備の傷み具合、劣化状況を専門家が細かくチェックし、報告書としてまとめてくれます。ぱっと見では分からない内部の損傷や隠れた不具合を把握できるため、今後の活用方針を決める上で非常に参考になります。
売却を考えている場合、こうした診断結果が物件の信頼性を裏付ける資料として買主の安心感につながり、成約を後押しするケースもあります。
空家を「維持」するか「手放す」かを検討
空家の活用・処分には、以下のような選択肢があります。
•維持管理し、将来利用や賃貸に備える
•老朽化が激しい場合は解体処分する
•売却して現金化し、維持コストを回避する
相続人が遠方に住んでいる場合や、利用の予定がない場合は空家売却を選ぶケースが多いです。特に固定資産税や保険料などの維持費が重くのしかかってくるため、「とりあえずそのままにする」という選択はあまり得策とは言えません。
売却の際に注意すべきポイント
空家を売却する場合、いくつか注意点があります。
まず、査定の段階でリフォームが必要かを見極めましょう。古い家を無理に全面改修しても、費用に見合う売却価格にならないこともあります。最低限の手直しで済ませ、価格と費用のバランスを取ることが肝心です。
また、前述の診断結果や登記情報など、買主が安心できる材料を事前に整えておくことで、売却活動がスムーズに進みやすくなります。
さらに、売却中の空家が放置状態だと、外観の劣化や雑草の繁茂などが起こり、物件価値を下げてしまう可能性があるため、最低限の維持管理は続けることが望ましいです。
放置によるリスクは意外と大きい
相続した空家を放置すると、思わぬ問題に発展することもあります。たとえば、老朽化による倒壊や、害虫・害獣の発生、さらには不法侵入によるトラブルなどです。
さらに、行政から「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇が外れたり、改善命令や罰則の対象になったりすることもあります。
空家相続後は「判断」と「行動」がカギ
不動産を相続した瞬間から、あなたはその財産の管理者となります。空家は、持っているだけで維持コストや責任が発生するため、放置せず早めに判断・行動することが重要です。
相続登記、建物状況の確認、売却か維持の選択——どれも難しそうに感じるかもしれませんが、専門家の力を借りれば、確実に前に進めます。
「どうすればよいかわからない」と感じたら、ぜひ不動産の相続に詳しい専門会社にご相談ください。状況に応じたベストな選択肢をご提案いたします。